1回目(Report①)と2回目(Report②)の間の移動時間を利用して、別の種類の分科会へ移動できます。
| 分科会名 | 9:30~11:00 | → | 11:15~12:45 |
| 1 小学校・中学入門期の指導 | 1 | 移 動 時 間 | 2 |
| 2 教科書・自主教材と読み取り | |||
| 3 英文法をどう考え、どう教えるか | |||
| 4 音声によるコミュニケーション | |||
| 5 学力と評価 | |||
| 6 仲間と学ぶ協同学習 | |||
| 7 遅れがちな学習者の指導 | |||
| 8 自己表現 | |||
| 9 平和・環境・人権・SDGsの 教育に取り組む |
6 仲間と学ぶ協同学習
フェアトレードを考える 協同的な学び
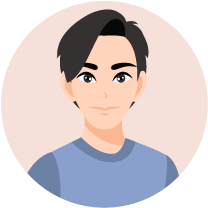 | 新井雄大(あらい・ゆうだい) (埼玉・中) |
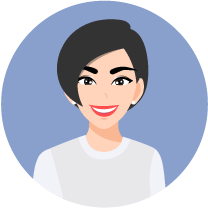 | 師岡美奈子(もろおか・みなこ) (埼玉・中) |
協同学習を授業に取り入れてから約10年となる。
協同学習をするかどうかの議論から始まり、協同学習を用いて教材の中身を深めたり、協同学習を通して和訳を更に発展させる授業展開ができたりと、ここ数年で授業の質がより高まってきている実感がある。
分科会では、中学3年生で扱うフェアトレードの単元をもとに生徒の変容などを報告し、協同で学びを深めるための手立てについて考えたい。
リテリングを超える? Literature Circleの実践報告

田口貴彬(たぐち・たかあき)
(富山・高)
新学習指導要領の施行に伴い、求められる授業の在り方も刻々と変化している。特に、広く行われているRetelling活動の在り方に疑問を感じ、改善を図った。本取組では高校における教科書主体の一斉授業において、主体的・対話的で深い学びを実現させるため、Literature Circleという活動を取り入れた。
本校で行った、生徒一人ひとりが異なった役割で教科書本文の内容を読み直し、発表を行うというこの取組について発表したい。
7 遅れがちな学習者の指導
英語が苦手な生徒でも 主体的に参加する授業を目指して
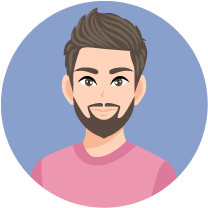
宮崎 遼(みやざき・りょう)
(埼玉・高)
定時制高校には様々な理由から基礎学力に課題を抱える生徒がたくさん在籍しています。そうした生徒の実態に合わせて授業を工夫し、わかりやすく丁寧に教え、生徒の学習意欲を高めていくことが定時制高校の教員には求められています。
「英語コミュニケーションⅡ」の授業で実践した「足場かけ」や「ICTとルーブリックを活用した音読活動」の例を紹介しながら、英語が苦手な生徒でも主体的に参加する授業についてご報告させていただきます。
「英語を分かりたい」という切実な願いに応えたい!

縣 文佳(あがた・ふみか)
(福岡・中)
「もう!英語が全然分からん!」と生徒に言われた経験はありますか。私は、何度もあります。自分の教え方について、何度も思い悩みました。そんなとき、「分かってほしい」という自分目線の考えから「分かりたい」という生徒の願いに応えたいという視点に、自身を転換させる出来事がありました。
「英語を分かりたい」という生徒の切実な願いに応えることを目指した授業づくりについて、みなさんと一緒に考えられたらと思います。
8 自己表現
「なりきり表現」で広がる思考の世界
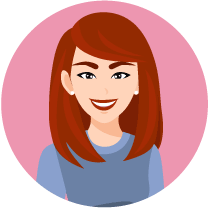
徳久君恵(とくひさ・きみえ)
(福岡・中)
自分のことを表現する自己表現に加えて、自分ではない誰かや、何かになって表現する「なりきり表現」で広がる思考の世界があると考えます。
教科書の本文で学習した戦後79年間ずっと同じ場所に建ち続ける原爆ドームになりきって(気持ちを想像して)表現した活動を紹介します。人(場合によっては物)の気持ちや考え、立場などを想像する力は、個人の考えに奥行きをもたせ、発想をより自由にすると感じています。
国際交流や体験学習で、自己表現したくなる状況作り

赤松敦子(あかまつ・あつこ)
(山口・高)
国際交流で様々な外国の学校の生徒さんと交流する機会を作ると、「相手に自分や日本のことを伝えたい!」「相手に教えてもらう趣味や外国の文化の話が面白い!」「思いやりが感じられる言葉のやり取りで、心が温まった」といったコミュニケーションの楽しさで、自己表現の意欲が高まるのではないでしょうか? また、着物着付け体験や外国料理の調理などの体験学習を取り入れると、体験したことを伝えたいという刺激が増えました。
9 平和・環境・人権・SDGsの教育に取り組む
世界につなげる自分の日常:平和・人権・環境の視点で

阿部始子(あべ・もとこ)
(山梨・小中大)
「国際理解教育」と「外国語教育」の融合を模索する上で、平和・人権・環境は私の実践の重要なテーマであり続けています。
本発表では、ウクライナの戦争を通して平和についてドイツの小学生と共に学んだ小学生が、中学生になって再びこのテーマに取り組んだ様子や、教員を志す様々な国の学生がIdeal Inclusive School(人権)について議論したり、日常生活の「自己実験(self-experiments)」を通して環境について考え行動した様子などについてお伝えします。
海外事情や国際交流をギミックとした授業
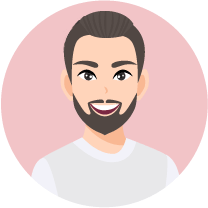
竹島 潤(たけしま・じゅん)
(岡山・中)
「学びに向かう力・人間性等」を育む英語の授業とは、どのようなものだろうか。それは、外国語4技能を習得することに加えて、生徒たちが自分と向き合ったり、自分を高めたり、他者とつながったりする力を伸ばせられる授業ではないだろうか。
「平和・環境・人権・SDGs」などの視点が、意図的な仕掛けと感情への揺さぶりを生み出す「ギミック」として、英語授業や言語活動に組み込まれたらどうなるだろう?
