★補助資料のダウンロード先URLは、7月29日(火)にメールでお知らせします。
★オンライン参加のURLも、同じメールでお知らせします。
第2日 1 9:30~11:00 2 11:15~12:45
1回目(Report①)と2回目(Report②)の間の移動時間を利用して、別の種類の分科会へ移動できます。
| 分科会名 | 9:30~11:00 | → | 11:15~12:45 |
| 1 小学校・中学入門期の指導 | 1 | 移 動 時 間 | 2 |
| zoom併用 2 教科書・自主教材と読み取り | |||
| 3 英文法をどう考え、どう教えるか | |||
| zoom併用 4 音声によるコミュニケーション | |||
| 5 学力と評価 | |||
| 6 仲間と学ぶ協同学習 | |||
| 7 遅れがちな学習者の指導 | |||
| 8 自己表現 | |||
| 9 平和・環境・人権・SDGsの 教育に取り組む |
1 小学校・中学入門期の指導
言語活動を通して 他者と触れ合う授業づくりを
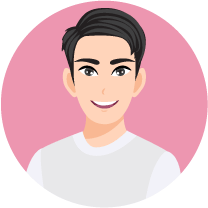
佐藤大樹(さとう・ひろき)
(埼玉・中)
私は1年間、中学1年生の授業を担当した。その中で、英語嫌いな生徒を増やさないこと、自己表現の機会を充実させること、そして生徒に、英語の授業が楽しいと思わせることを大切にしてきた。今回の実践レポートでは、生徒のリアルな声と、実践した言語活動を紹介し、その成果と課題を考察する。
参会者の皆様と、小学校での学びを中学校へ繋げ、深めるための指導、工夫を考えたい。
コミュニケーション能力の素地・基礎を養うこと
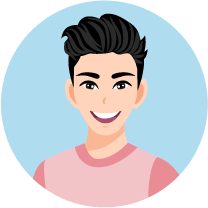
松永桂佑(まつなが・けいすけ)
(大分・小)
小学校では、中学年で外国語活動、高学年では外国語の学習が行われています。
コミュニケーション能力の素地や基礎を身につけた子どもとは、どんな姿なのかを考えて試行錯誤しながら実践を行っています。その中でも、コミュニケーションの目的設定や他者に配慮しながら伝えること、語彙の獲得に関わる考え方や指導について振り返り、議論ができるようにこのレポートを提案します。
zoom併用 2 教科書・自主教材と読み取り
単元を通した発問で読解を深め、その先にあるものは?
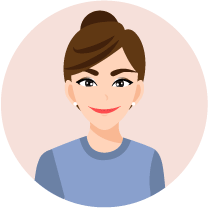
尾張至伸(おわり・しのぶ)
(青森・中)
New Horizon 中学3年の長文(約300語)読解の実践を紹介する。発問と音読劇を活用することで、生徒の内容理解がより深まった。特に今回は、単元を通した発問:Big Questionを設け、それに関わる事実発問や評価発問を繰り返し、単元の最初と最後で、同じ発問を繰り返す工夫により、生徒の考えが変容した。
その経過を報告し、皆さんと読解における発問の意義や教育的効果について話し合いたい。
読解指導の教材研究

斉藤 貴子( さいとう・たかこ)
(埼玉・高)
「読解指導の教材研究はどのようにするのか」という問いに的確に答えるのはなかなか難しい。
定年間近ですが、ここ数年ようやく教材研究のフォーマットができてきたのでそれを交流します。
★申し訳ありません。都合により、当初予定していたレポート・レポーターから変更になりました。(6/22)
3 英文法をどう考え、どう教えるか
中学生の語彙力を補う 前置詞の学習
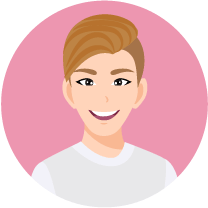
羽野祐司(はの・ゆうじ)
(大分・中))
小学校で外国語が教科となり、子どもたちは中学校入学前にたくさんの英語に接している。しかし、小学校で学んだ語が定着しているとはいえない状況で中学の学習がすすんでいる。
今回は前置詞に焦点を当て授業で語彙力を補充する学習法を考えてみた。それぞれの前置詞がもつイメージを大事にしながら、帯活動で段階を追って習得させる方法を提案したい。
英語の歌と文法指導 ~歌が先か? 文法が先か?~
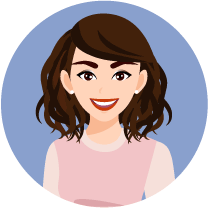
橋山芳子(はしやま・よしこ)
(滋賀・高)
英語の歌で授業を始めると、これから英語の授業が始まるという雰囲気ができ、英語に苦手意識を持つ生徒も楽しめます。Authenticな英語の聴き取り・発音・読解練習ができ、重いテーマにも身構えることなく取組めました。文法に合わせて歌を選ぶのが一般的ですが、まず時期や生徒に合わせて歌を選び、既習の文法事項が含まれる歌詞の和訳や語順整序に取組んで、文法を復習しました。生徒にウケた新しい歌も紹介します。
zoom併用 4 音声によるコミュニケーション
小中高からシニアまで、みんなで楽しむ英語音声指導!
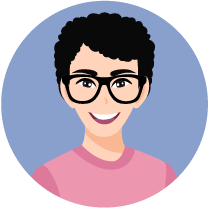
海木幸登(かいき・ゆきと)
(富山・元高)
「楽しくなければ英語じゃない!役に立たなきゃ技術じゃない!!哲学なければ教育じゃない!!!」―90分があっという間の楽しいエンタメ流・音声指導講座です。登場する人物は谷川俊太郎、和田アキ子、堀内孝雄、ヘップバーンなど多数。そして登場する指導法は、「生徒の音が変わる指示」「七色の音読」「トイザラス読み」「10回音読」など。「雨に唄えば」「英国王のスピーチ」「トリセツ・ショー」など映画やTV番組もたくさん登場します!
脳と心と集団を鍛える話すこと[やり取り] 〜校種を超えて~

武田千絵(たけだ・ちえ)
(広島・高)
話すこと[やり取り]を通して、どのような力を育むのか。AIの時代となった今だからこそ、コミュニケーションの重要性や教室での学びについて、改めて考えてみたいと思います。
今回は、中学校教員としてスタートした私が、その経験を基に挑戦した小学校と高等学校での実践をご紹介します。会場の皆様とともに、校種を超えて、「話すこと[やり取り]」の指導の難しさやおもしろさを共有できればと考えています。
5 学力と評価
教室を世界とつなごう ~リアリティを伴う外国語教育~
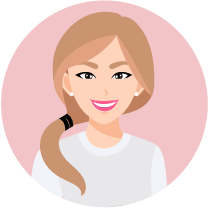
新野ゆかり(にいの・ゆかり)
(北海道・小)
14年ぶりに帰国した日本で、外国語専科教員という職に挑戦するにあたり最も重視したのは、『英語はコミュニケーション・ツール』を子どもたちに実感してもらうことでした。そのために様々な方法を駆使して小さな教室を“本物”の広い世界とつなぎ、リアリティを伴った授業を心がけています。
試行錯誤の中で生まれるライブ感を子どもたちと共に愉しみ、予期せぬ成功や失敗を丁寧に拾いあげて次の課題につなげていきたいです。
基礎から応用へ、成長を実感できる授業を考える
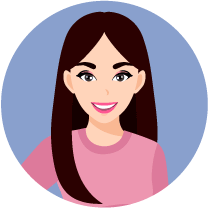
大賀晃代(おおが・あきよ)
(大阪・高)
授業の中で表現活動を取り入れる際、活動だけを行っていてもあまりうまくいかない。ではどのように授業を組み立てたらいいだろうか。生徒たちが自分の意見を英語で表現できるようになるためには、基礎力定着から順に段階を経た指導が必要である。
日々の授業で取り入れている基礎トレーニングから表現活動に向けて、生徒自身が成長を実感できる授業作りを考える。
