各校種における課題に取り組む授業実践から学ぼう!
★補助資料のある分科会については、ダウンロード先URLを7月29日(火)にメールでお知らせします。
★オンライン参加のURLも、同じメールでお知らせします。
第1日 15:30~17:00
zoom併用 Ⅰ 小学校
世界とつながる「生きた英語」をめざして
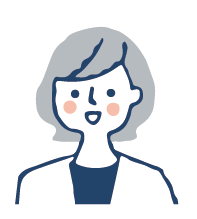
山西由起(やまにし・ゆき)
(山口・小)
小学校外国語の授業の発展として行った国際交流の様子を紹介します。これまでオーストラリアやフィンランドなどの小学校と交流してきました。その成果は、英語での本物のコミュニケーションを体験できたこと、子どもたちの様々な国への関心が高まったこと、自分や日本について発信したいという思いを深めたことです。
交流を通して、英語でのコミュニケーションや世界とつながる楽しさを実感した子どもたちの声をお伝えします。
Ⅱ 中学校 ①
「ことばが生まれる」ために 集団学習から個人の表現へ

若杉玲恵(わかすぎ・さちえ)
(埼玉・中)
国際バカロレア(IB)認定校で,探求を基盤とした授業を行っています。IBの教育はよりよいより平和な世界の実現を目的としており、新英語教育研究会との親和性があるように思います。中学2年生が授業の中で社会問題の解決に向けた探求を行い、グループ活動後に、生徒が個人で表現したことついてお話します。
生徒が自由に存分に自分の英語で表現するために、教師ができることについて皆さんと探し求めたいと考えています。
Ⅲ 中学校 ②
災害時の外国人に寄り添う防災アドバイス
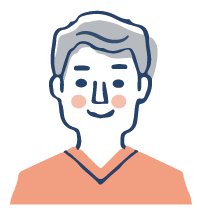
内記大地(ないき・だいち)
(富山・中)
相手意識をもち、つながりとまとまりのある英語を生徒に表現させたいと考え、単元末にALTの先生に向けて防災アドバイスを書かせた。相手が必要としている情報や相手の気持ちを考えた内容を生徒に書かせるために行った指導の工夫を紹介する。そして、生徒の書いた英作文とパフォーマンステストの結果から分かる本実践の成果と課題を発表する。
zoom併用 Ⅳ 高校(比較的易しい)
対話を促す授業づくり~学校を出会いと学びの場に~
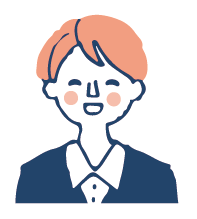
盛田彩花(もりた・あやか)
(長野・高)
様々な学習ツールが存在する現在、勉強は学校外でも容易にできるものになってきています。学校という場で学ぶことの最大の意義は、生徒同士が対話の中で学びあうことにあると感じています。一方で、いざ対話的な活動を授業に取り入れようとしても、なかなかうまくいかないことが多いことも事実です。
本レポートでは、「対話的な学習を促す」ことに重点を置いた授業実践を報告します。
Ⅴ 高校(比較的難しい)
文学と科学の融合 ~雪の結晶を通して~
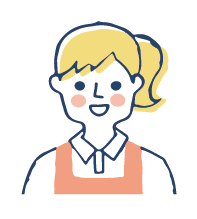
乾まどか(いぬい・まどか)
(大阪・高)
CLIL(内容言語統合型学習)を活用した高等学校教科横断的授業の実践の報告である。英語、理科、国語を統合し、英語教科書 “Snow Crystal” を基に教材を開発。寺田寅彦、中谷宇吉郎、夏目漱石の業績を題材に、気象学や文学的視点を取り入れ、関連施設訪問や英語での実験も行った。生徒の探究心や学習意欲向上を目指した。科学的視点と文学的感性の育成に効果的であることが示唆されている。
Ⅵ 高専・大学
CLIL授業「言語教育法」でトランスランゲージング
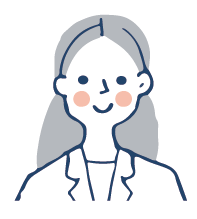
戸出朋子(とで・ともこ)
(広島・大)
トランスランゲージング教育論は教育の脱植民地化を目指す実践理論で、新英研の理念に通底します。報告者は、CLIL授業「言語教育法」をトランスランゲージングの精神を生かして行いました。学生が言語学習・教育について考え、交流し、自己の言語学習を肯定的に見る授業です。
発表では、トランスランゲージングの鍵概念を述べた後、英語・日本語・あらゆるリソースを使って学生たちがどう表現し、何を考えたかを報告します。
Ⅶ 特設 ICT
ICT活用の可能性と課題 ~実践から学ぶ効果的な使い方~

奥田紀子(おくだ・のりこ)
(愛知・高)
ICTを活用することで、学びの幅が広がり、協働の促進につながる場面が増えます。しかし、使い方によっては集中力が途切れるなどの課題もあります。
ICTは決して得意ではありませんが、実践を通じて感じた「効果的な活用法」と「気をつけたい点」を共有し、より良い使い方を考えたいと思います。現場目線での気づきを大切にしながら、誰もが活用しやすい方法を一緒に探っていきましょう。
